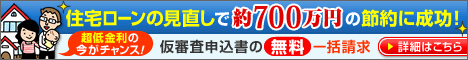住宅ローン 金利上昇時のリスク回避方法とは
住宅ローンの金利の今後の動向は、どのようになっていくのでしょうか?
大変気になりますね。
2006年7月14日、日銀が、「ゼロ金利政策」の解除を決定し、無担保コール翌日物金利(金融機関同士が資金を貸し借りするコール市場で、翌日には返済する貸し借りの金利のこと)を0.25%前後に推移するように引き上げ、即日実施しました。
このことを受けて、短期金融市場における通常の金利が復活することになりました。
今後は経済・物価情勢を見ながらの「市場メカニズム」で金利が決定されていくことになりそうです。
今後の方向として、金利は、上向きの線を描くことがほぼ確実になると考えられています。
すなわち金利は上昇傾向にあるということです。
もっとも、日銀総裁が、「極めて低い水準を当面は維持する可能性」を示唆している以上、
日本経済にショックを与えるような急激な上昇は、まず当面は考えられないとは思います。ただし、あくまでも当面という短期的な話ではあります。
ちなみに2006年11月現在の住宅ローン長期固定金利は、前月比0.15%〜0.20%上昇。
長期固定以外の2年〜3年短期固定も同様に上昇しています。
今後住宅購入をお考えの皆様にとって、住宅ローンの金利については、非常に気になるところでありますよね。
そこで、金利上昇時のリスク回避の方法についていくつかご紹介したいと思います。
その1 住宅ローン全期間固定金利型を検討してみる
「フラット35」のような全期間固定金利のローンの検討をおすすめします。
最近は、全期間固定金利や超長期固定選択型(20年〜)の商品が充実してきており、それぞれ単独で借り入れを行ったり、フラット35と併用する方法なども用意されています。
その2 「変動金利型」と「全期間固定型」のミックスタイプを検討してみる。
「変動金利型」と「全期間固定型」を例えば半々ずつとかミックスされているタイプのローンです。それぞれの金利が持っているリスクを分散させるということで影響を緩和できる可能性があります。
その3 住宅ローン金利の上昇を抑えるタイプを検討してみる
市場金利が上がっていっても、一定の水準から金利が上がらないタイプの住宅ローンがあります。いわゆる「上限金利付きの住宅ローン」です。
変動金利型に属するのですが、当初の金利は通常の変動金利よりも高く、固定金利選択型よりも低い水準から始まります。半年毎の適用金利の変更が発生しても、決められた期間中にある上限に達した場合はそこからは上がらないというものです。
この上限金利を頭に入れた上で、余裕を持って返済が可能な場合、上限金利になってしまった期間に、まとまった金額で繰り上げ返済が行えそうな場合は、検討されてみるとよいと思います。
その4 借入れ額を少なくする
金利が上昇するということは、借り入れ額の利息も増加してしまうということです。
借入額そのものを少なくすれば、その分、金利上昇のリスクは回避できるといえます。
いたってシンプルであたりまえの理屈ではありますが、意外と見落としがちですので
念のためにご紹介させていただきました^^
借り換えの場合は、より低金利の長期固定型への移行を検討されるとよいでしょう。
ご参考までに
主要金融機関の金利比較グラフを掲載しているサイトをご紹介しておきますね
こちらです。→http://www.nikkin.co.jp/kinri/house.html